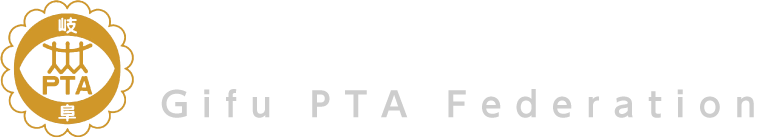オリンピック7人制ラグビー女子日本代表
日本代表を目指した娘(竹内亜弥)と共にー食べる力・考える力・自分でいる力ー

岐阜薬科大学 先進製薬プロセス工学研究室 特任講師
竹内淑子
わが子のあゆみ・486号 特集記事 より
1 オリンピック―リオ五輪観戦(サクラセブンズとともに)―

2024年パリオリンピック・パラリンピックでの熱戦の様子が記憶に新しい。
2016年8月には、ブラジル・リオでオリンピックが開催された。
私たち家族は、その観戦に向かった。成田空港からドバイまで十時間、ドバイからリオまで十四時間と、本当に丸一日掛かって、8月4日「太陽の国ブラジル」のリオに着いた。
このオリンピックから、7人制ラグビーがオリンピック種目となった。
しかもなんと、我が家の次女は女子ラグビーの選手であり、オリンピックのフィールドに立てるかもしれないからだ。「かも…(?)」というのは、当初、娘は女子日本代表登録メンバーから外れてしまったからだ。登録メンバー以外に、チームに帯同し不測の事態に備えるメンバーのことをバックアップメンバーと言うらしい。登録メンバーと同じように練習、コンディションの調整に努めながら、チームを応援・支援するが、選手村には入れず、もちろんグランドには立つことはできない。通常、国内におけるシリーズ、ワールドカップなどの7人制ラグビーの試合では12番までしか登録されず、オリンピックだけの特別ルールで、背番号14番までが許されていた。13番、14番の選手は、基本的には出場機会はなく、その後の展開で出場できるか、できないか、分からないということだ。娘は、日本チームの背番号13番を頂いた。
娘からは、出発前に「お母さん、バックアップメンバーに回された。忙しかったら、リオに来なくてもいいよ。私は、リオまで帯同する。」と落ち着いた口調で電話をもらった。
「行く、行く。絶対に行くよ。」と即答したものの、アジア予選のときには代表選手として全試合出場し、数日前の壮行会までは、日本代表選手として選考、挨拶もさせて頂いていたのだから、本人も落胆しているはずである。一体、どんな気持ちなのだろう?わざわざ私たちに電話してくれるなんて…、と考えさせられた。それなのに、遠路ブラジルまで応援?と思われる方もおられると思うが、本人はさておき、とりあえず行っておこうと言う感覚(?) であった。
8月6日、いよいよオリンピック史上初の7人制ラグビーの試合が行われる日である。何はともあれ、地球の裏側まで連れてきてくれた娘亜弥とサクラセブンズ(7人制ラグビー女子日本代表の愛称)の皆さんにまず感謝し、辿り着いたリオのスタンドで観戦した。
黄色・黄緑・オレンジ・水色の座席が波打つように輝いていた。各国女子ラグビー選手が史上初のオリンピックセブンズラグビー選手となる。
「ここで、戦うんだなあ」と感慨もひとしおであった。
一日目、第二戦、対イングランド戦の途中、日本選手が一人フィールド外に搬送された。途中退場の選手はFWの中心選手、脳震盪だった。以降の試合には、出場できないかも…その夜遅く、総務の方から、退場した選手の両親に電話。やはり、出場できないことになった。
二日目、ケニアとの対戦。インターセプトを含めた果敢な攻めで試合を進めていく。17―0で後半残り2分半(一試合:前半7分、後半7分)となったとき、二名の選手が交代出場してきた。11番チーム最年長の兼松選手とバックアップメンバーから追加登録された13番の竹内亜弥。娘は奇跡のように、オリンピアンとなった。
その試合で日本チームは無事オリンピック初勝利を挙げることができた。娘も、何とかチームのために、怪我をされた選手に代わって働くことができた。その後もう一試合に出場が叶った。そして彼女の熱い夏の日々は終わった。
2 のびのび岐阜育ちそしてオリンピックへ
娘は幼少より性格は明るく、運動が好きというよりは、岐阜の自然豊かな野原を走り回るのが好きな子だった。小学校時代は、仲良しのあずさちゃん、まいちゃん、たかお(2歳下の弟)、あや(本人)の名前から「たあまあ隊」と称して、よく戸外を遊び回っていたのが懐かしい。出身の岩野田北小校下は、遊び回れる所が多くて幸せだったと思う。
また、我が家は、スポーツ好き家族で良くいろいろなスポーツをして遊んだ。実家近くの椿洞「畜産センター」の広場では、一日中ドッチボールをした。おかげで、私は肩が上がらなくなった日があった。河川敷ではコートを書いてテニスの真似事もした。
しかし残念ながら、遺伝的にアスリートの血を引いているわけではない。女子日本代表の選手の中には、「父親・兄がラグビーをやっているのを見て、5歳から始めました。」「母が陸上社会人チーム出身で、父は有名高校のラグビー選手でした。」「お母さんは、大柄な選手、本人よりももっと大柄です。」という方もみえた。そう聞くと、両親ともにアスリート未満(=「スポーツ好き一般人」)の私たちからは、与えられるものが特に何もなく、私は本当に申し訳なく思った。

私たちは、娘のオリンピアンへの道は決して平坦なものではなかったことを見てきた。信じられないほどの山あり、谷ありの道のりだった。
中学・高校は愛知県の滝学園に進学、京都大学卒業後に草ラグビーを始めた。そんな時、ちょうど7人制ラグビー競技のオリンピック採用が決まり、それに伴い、女子ラグビーの強化も始まったらしい。男子ラグビーと違って母数の少ない女子選手をさらに獲得するべく、他競技からの選手の発掘が行われることになったという(トライアウト)。中・高・大学在籍中はバレーボール部に所属し、年齢も募集枠に合致しているということで、お世話になっていたチームからの推薦で、娘も代表トライアウトに参加させてもらった。
2009年トライアウト初挑戦、結果は保留、その後、残念ながら、3回落選。幼い頃から励んできておられる代表選手や他競技で実績を残してきた転向組の参加者に比べると、フィジカルは高いものの、経験値・スキル・速さが十分ではないためであったと思う。
ところが、この落選の悔しさをバネに、当時勤務していた出版社(㈱新潮社)への通勤前にトレーニングに励んだという。
そんな時期、ある試合に出場していると、「あの黄色いシューズの子は誰?」と日本代表チームヘッドコーチの方の目に留まったらしい。それがきっかけとなり、女子の日本代表スコッド入りをした。
しかし、スコッドというのは、あくまで代表を選ぶための候補選手であるらしく、代表ではない。そのためなかなか日本代表として遠征に選ばれることもなく、もちろん代表の試合に出る機会もなかった。
数年後にやっとアメリカ遠征に参加でき、代表戦に投入してもらうことができた。その後、2013年7人制ワールドカップではモスクワまで行ったが、バックアップメンバーとなりベンチに入れず、もちろん試合にも出場できなかった。
2016年リオ五輪でも、最終的には代表選手として参戦させてもらえたものの…親はいつもハラハラドキドキの体験だった。しかし、こんな経験の中でも、娘は最後まで「あきらめずに努力」し続けてくれた。
たった数分ではあるが、オリンピック出場のチャンスを得たのは、本人がひたすらその時に備えたからだと信じている。私には、この事こそ価値があり、親として最も嬉しく、誇らしいことだと思える。それは彼女自身の特性によるものだ。もし、親として貢献したことがあるとすれば、ひたすら本人のやりたいことを邪魔しなかったこと、反対しなかったことだと思っている。
「できない事に立ち向かうのが、チャレンジ。できることをするのはチャレンジではないから…」と思っていたと推察する。

3 子育てで親ができることとは?
オリンピック出場後、色々な場面で選手の母親として質問されることがあった。「お嬢さんがラグビーを始められた時はどう思ったか」「平均的なことから外れても許容できたのはなぜか」「子育てで大事にしたことは何か」等々。そこで、あれこれ考え、子ども達と共に過ごした日々を思い出してみて、「大事にしたことは」、以下のような「…力」を養うことだった。
①「食べる力」
現在、私は4人の孫の祖母となり、時々、娘たち家族と食事をする。その際、娘たちが孫たちに「ばあばは、ご飯とお行儀にだけは、うるさいんだからね!」と声を枯らすのを聞き、そんなにうるさかったかな?と振り返ることがよくある。
母であった時代、私の思いとしては、何を置いても、体力一番。将来、どのような道でも、自分の好きな道に進んでもらえば良いが、その道を歩み続けるためには、平凡ながら心身の健康が必要。そこで、そのためには、やはり食事が基本、大事という思いからである。どのお母さんもみなさん、そう思っていらっしゃるであろう。しかし、そんな親の願いに反して、子ども達には好き嫌いがあり、出された食事量を完食できるかどうかは、個人差・コンディションの差によるのは当然だと思う。
もちろん、食事を前にして、自分(母親)がどんなにまずいご飯を作っていても、「残さず食べなさい‼」と言うわけだが、その次にどうしても食べきれないときは、「半分は、食べなさい!」、その次には「一口は、食べなさい~」と譲歩する言葉を用意していた。その甲斐あって、子ども達は、もちろん好き嫌いはあっても、食卓に出た食事は残すことなく食べてくれるようになった。「お肉嫌い!野菜嫌い!」「いいですよ。だけど、チャレンジはしてね!」後に、ラグビーは卑怯なことをするのが最も嫌われるスポーツだと聞き、得心した。逃げずに何でも食べてね!
娘に関して、とてもうれしいエピソードを聞いた。
日本代表合宿に呼ばれた際、初召集の選手には食事の時に決められたルーティンがあるという。それは、鬼のストレングスコーチ(見た目が怖い!実は、優しい方なのですが…)の正面で食事をすることであった。食の細い選手は、なかなか合格が出ないらしいが、偏食なし、かつ、大食漢の娘は、誰よりも早く、さっさと卒業したと聞き、「成果があった!」とほくそ笑んだ。
代表選手に選んで頂けることも嬉しいが、この話を聞いた時には、一番大きくガッツポーズをした。これ、母のお陰‼
その結果だと信じているのだが、娘にはチーム内でのあだ名があった。ヘッドコーチの方も公認の「鉄人」「鬼の回復力」である。
ラグビーはご存じの通り、怪我の多いスポーツだ。娘もラグビー日本代表に選ばれ始めると、怪我をすることが増えた。初めて鼻を骨折した時には、勤務地の東京まで呼ばれて、病院で手術の終了を待機した。福岡での試合観戦に行った折には、いつの間にかフィールドから本人が消えており、どうしたのかと思っていると携帯電話がなり、「今、救急病院から帰ってきたので、~まで来て!」と本人から呼び出された。行ってみると、目の上が腫れ上がり、目の周りが青くなった顔で経緯を説明された。その後、鼻の骨折数回など…。しかし、その後は一向に知らせてもらえず、すべて事後報告となった。正確には、数えきれないらしい。
そんな折、一番に本人が言うには、「みんなにまた鬼の回復力って言われたよ。」ということであった。しかし思い返すと、娘は小さい頃、よく転び、よく怪我する子供だった。多分、原因は目的に向かって、脇目も振らず、前傾姿勢で、全力で走り過ぎていたためであると推察する。「よく食べ、よく寝た」からか、お陰で強い子になった、ただし無謀にもなった。親はただ、「好き嫌い、言ってもいいけど、ご飯は食べてね!」と言うだけだった。
「おかあさん、丈夫に産んでくれて、ありがとう。」と言われたことがあるが、「こちらこそ、ありがとう!丈夫に育ってくれて!」だ。長じても子どもの怪我と病気は辛い。良かった。「食べる力」のお陰だ。
②「考える力」
「子どもに勉強を好きにさせるのにどんな取り組みをしたか?」と質問されることも多い。完全な答えはないが、とりあえず「読書」だったと思う。
私自身が、読書好きということもあって、子ども達にもよく本を読んであげたし、本人にも読んでもらった。今でも、よく笑われる話がある。就寝時に絵本を読み聞かせるのだが、途中で自分が先に眠ってしまい、「おかあさん、そんなこと書いてないよ~」と、子ども達に指摘され、気が付くと全く違う内容を夢の中で自作して読んでいた。
また、よく顔の上に絵本を落として痛い目をみた。教えていただいた岐阜市立の長良図書室で子どもといっしょによく本を借りた。一人5冊ずつ、五人家族で25冊まで借りられるのをとても喜んでくれた。クリスマスプレゼントも、本と希望の物と決めていた。それぞれの子どもにその時最適の本を選ぶ事に全力を傾け、成功または失敗と、一喜一憂して楽しんだ(親の自己満足)。本を選ぶ基準は単純だが、ためになるよりも自分が読んで面白い本、楽しい本とした。無理なく読み進んでもらえるように考えた。後年、読書好きの娘は出版社に勤務させて頂くこととなった。
さらに遡れば、「勉強するということは?」という課題もある。私自身は「勉強する」とは、興味を持ったことを追求することだと信じている。大事なことは、考えることで、考えたくなる好きをみつけることだ。これを子ども達に実践してもらうには、まずは勉強の仕方を考えてもらうことではないかと思っている。やりたくないただの勉強(試験勉強など)でも、自分で決めたルールで自分に適した方法を見つけ出せれば、結構楽しんで進められる。「自分の・自分による・自分のための」勉強の仕方を考えることは大事だ(えせリンカーンのようだが…)。娘は、幸い勉強法がとても上手になり、一例としては、参考書、資料集をカットしてルーズリーフ状にする軽量化(携帯に便利)、数学の問題は白紙ノートで解く(実践対応)など、面白い方法があった。私も参考にさせてもらっている。娘は、大学では文学部哲学科哲学に進んだ。哲学とは、考える事だが…「考える力」は身に着けたのか?
③「自分でいる力」―鈍感力って何?
娘が所属していたラグビーチーム(ARUKUS QUEEN熊谷)の方から、「娘さんは鈍感力に優れているが、何か育児で鈍感に育てたことはあるのか?」という問いがあった。「そんなに鈍感なんだ…」、「どうやったら、わざわざ鈍感に育てられるんだ…」と笑いつつ、お褒めの言葉と理解して、考えてみることにした。先ず、『鈍感力』(渡辺淳一著、集英社)を購入して開いてみた。2009年に流行した言葉だが、タイトルだけは知っていたものの、まだ手にしていなかった本だった。著者のお言葉から、「鈍感力」とは?というキーワードを抜粋してみると、のんびり/おおらか/くよくよしない/前に向かって進む/楽天的/したたか/強く健康/へこたれない/タフ/立派/逞しい/明るい/前向き/めげない/立ち直る/打たれ強い/失敗、ミスを忘れる/あまり感じない/人の話を真剣に聞かない/図に乗る……
思わず笑い転げるほどピッタリ当てはまる。「人の話を聞かない」「図に乗る」、これ、これ、この通り。なるほど、確かにこれだと思い当たった。もちろん、親の言うことも聞かないが、自分で決めたことは、達成していた。自分で納得して失敗すれば、痛みにも耐えられる、そもそも、痛くないのか、「感じない」のかもしれない。
『長い人生の途中、苦しいことや辛いこと、さらには失敗することなどいろいろある。そういう気が落ち込むときにもそのまま崩れず、また立ち上がって前へ向かって明るく進んでいく。そういうしたたかな力を鈍感力といっている』(同著より)
大いに「鈍感力を持っている」と認めよう。決して平坦ではない道を歩んで来た。落選、落選、落選!でも、確かに、娘は人の目を気にせず、人の評価を気にせず、ただし、人の(もちろん親の)言うことも聞かずに、なりたい自分に向かって繰り返し挑戦した。 人の評価を気にしないお陰で「何にでもチャレンジできる」し、前に進めたのだろう。そのため、自分がなりたいと思う人になれるのだろうと思う。自分が望む自分像を求めて、自分の、自分で選んだ、自分のための、「自分でいる力」だろうと納得できた。親がこのように育てようとしたことはない。多分、親も鈍感だった?!そんな時、親の勤めは「図に乗る子どもの邪魔をしない」ことだ。
4 おわりにー保護者の皆さんへ
親御さんは、誰でも「その子と」「その時」という意味ではいつも初心者だと思う。力不足で当たり前、悲観することなく、「その時」を大事に考え抜き、それぞれの「その子と」対峙し、「その時」を楽しむことをお勧めしたい。私自身も、三人の子どもを育てる中で分からない事ばかり(涙)。しかし、お陰で少し賢くなれた。「子育てでもっとこうしておけば良かったという事は?」の質問には、「もっと一緒に遊べば良かった」と答えたい。子どもと一緒に遊べる時期は意外と短い。
最後に、このような寄稿の機会を頂き、子育て時代を振り返り、楽しい記憶が蘇った。感謝いたします。皆さんのお子さんが、いろいろな力:食べる力、考える力、努力する力、へこたれない力、好きを見つける力、そして『自分でいる力』を身に付けられて、幸せに成長されますように願っています。
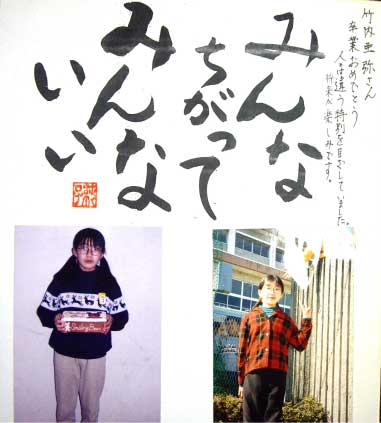
岩野田小学校卒業時に小野校長先生からいただいた色紙。
「ちがっていいよ」と言っていただき、とてもよく理解してもらっていた。